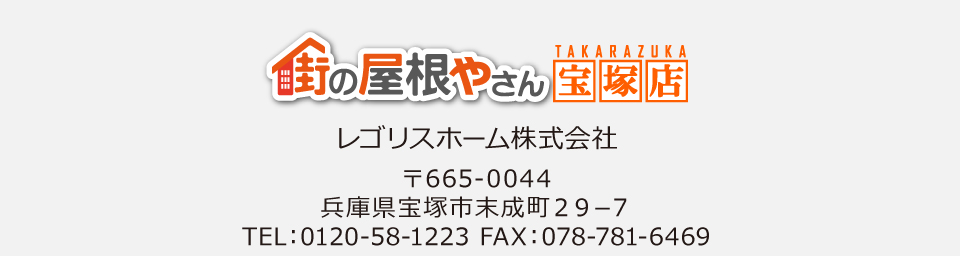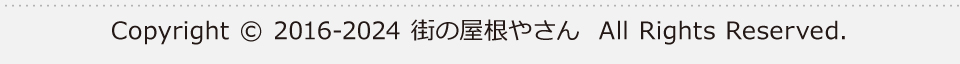2026.01.14
こんにちは!街の屋根やさん宝塚店、生クリームが好きな京谷です(*^^*)今日のブログは、神戸市北区で行った「この屋根将来どうする?アスベスト含有カラーベストの判断ポイント」という内容の記事を書いていきますね!!この記事では、カラーベストの特徴やアスベストとの関係について分かりやす…
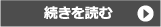



昨日、八千代折をした棟部屋根材の棟側に芯材を入れて、屋根下地のセンチュリーボードに届くよう、65mmのビスで芯材を固定していきます。
センチュリーボードはセメント成形の屋根用下地材で、構造用合板とは比較にならない強度を持っています。木造の一般戸建て住宅では使われることはなく、重量鉄骨造などの鉄筋コンクリート造並みに剛性が高い躯体の建築物で使用される建材です。
この下地材にビスを届かせて行きますから、電動工具や長手のバールでも使用しなければ、固定した芯材を浮かせたり、抜いたりすることは不可能です。
芯材が固定されたら、その上に貫板(ヌキイタ)を打ち付けていきます。ご覧のように大棟板金の納まり幅に添うように、固定していきます。芯材には90mmのビスを使用して、屋根下地材のセンチュリーボードに届かせますので、先の芯材の固定とともに強力な下地が出来上がります。
いくら頑丈で屈強な下地でも、直線が通っていなければ、曲がっている下地に添って、棟板金も蛇行してしまいます。
蛇行とは、蛇が地を這う時に鱗を動かせてクネクネと進んでいきますが、その蛇の動く様に似ていることから称される表現です。


建築業界では様々な場面で行う手法ですが、水糸を張って、先に一定の基準を作っておくのです。
この基準線から何mmの位置に固定すると決めると、簡単に直線を出して決めていくことができます。
アナログな手法ですが、人の感覚ほど優れた確認方法はありません。なぜなら、目で見てきれいなのかどうなのか、その感覚で仕上がりの判断が決まるからです。
美しいと感じるものは、大多数の人が美しいと感じるから、アナログな感覚は理屈にも勝るのです。


大棟の板金を仕上げて本日の作業を終了する見通しでしたが、天気予報よりも早く雨が降り出しました。

屋根工事の大敵は雨降りです。雨が降ると、仕上がる前の屋根では、即雨漏りにつながります。そして濡れた屋根はスケートリンクであるかのように、極端に滑りやすくなります。
屋根の上で作業をしている屋根職人さんたちの命が危ぶまれます。このマンションでは一番低い軒先でもおよそ10mの高さがあります。足場があるとはいえ、足場には隙間が設けられていますので、地面まで滑落する可能性も十分にあるのです。
一刻も早く作業を中断して危険を回避しなければなりません。しかし雨漏りをしない、させない屋根を作るのが屋根職人の仕事です。雨漏りが絶対にしないと言い切ることができる、切のいいところまでは作業を止めない職人魂が素晴らしい。大棟の板金を仮止めして、万一強風に見舞われても吹き飛ばされないように処置をして、本日の作業は終了しました。
街の屋根やさんご紹介
街の屋根やさん宝塚店の実績・ブログ
会社情報
屋根工事メニュー・料金について
屋根工事・屋根リフォームに関する知識
Copyright © 2016-2026 街の屋根やさん All Rights Reserved.