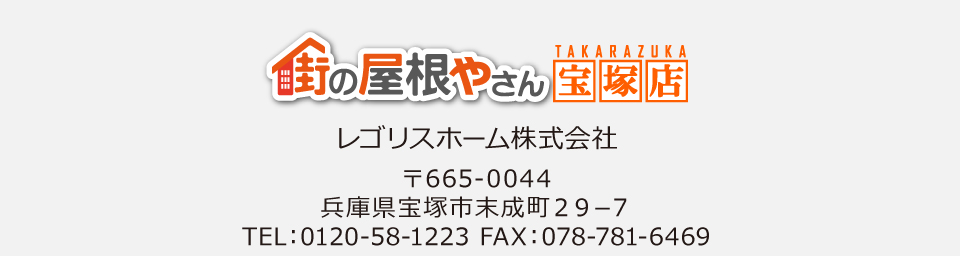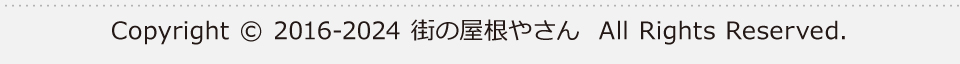2026.02.24
こんにちは!街の屋根やさん宝塚店です(*^^*)今日のブログは、淡路市で行った「銅板の穴あきを無料調査!原因特定と交換のススメ」という内容の記事を書いていきますね!!木造住宅に設置された銅板製雨樋は、長年の使用で劣化が進み、雨水が漏れている状態でした⚠️銅板雨樋は耐久性が高く、美…
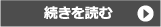
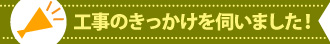
加東市のお客様より
「屋根工事を予定しているのですが、それに合わせて足場を利用し、雨樋の一部だけ交換できないかと考えています。
現在、一部の箇所で水漏れが見られる状況です。
全体を交換するとなると予算的に厳しいため、可能であれば必要な部分のみの修理で対応していただけると助かります。
現地の状況を一度見ていただき、部分交換でどのくらいの費用がかかるのか、お見積もりをお願いできないでしょうか?」
とお問い合わせいただきました。
現地調査を行った結果、雨樋の端部から水漏れが発生していることが確認できました。約6mの雨樋が対象となるため、その部分のみを部分的に交換するご提案をさせていただきました。
費用や施工方法についてご納得いただき、工事のご依頼をいただく運びとなりました。







今回の現場では、半丸型の軒樋が取り付けられていましたが、つなぎ目の部分から水が漏れている状態でした。
【ジョイント部分から雨水が漏れる主な原因】
経年による劣化
長年使用する中で、接続部に使われているゴムパッキンやシーリング材が劣化し、密着力が落ちてしまうケースがあります。
取り付け不良
継手がしっかり噛み合っていなかったり、固定が甘かったりすると、わずかな隙間から水が漏れてしまいます。
外的なダメージ
台風などによる衝撃や物がぶつかることで破損し、特につなぎ目部分に隙間が生じることがあります。
雨樋の寿命は一般的に20~25年程度といわれています。これを超えてくるとトラブルが起きやすくなるため、定期的な点検やメンテナンスをおすすめします。

今回の雨樋修理では、軒樋の部分交換を行います。
そのため、接続されている集水器や竪樋は破損しないように慎重に取り外しながら作業を進めていきます。
ただし、稀に経年劣化などで取り外しが困難な場合もあり、その際は竪樋を途中でカットし、軒樋交換後に再接続するという方法をとります。
雨樋の修理は現場の状況によって最適な対応が異なりますので、事前の点検時にしっかりと内容をご説明させていただきます。

水漏れの原因となっていた古い雨樋を取り外していく作業からスタートします。
作業にあたっては、いくつか気をつけるべきポイントがあります。
まず、安全第一で進めるために、安定した足場や脚立を使い、転倒や落下を防ぐ体制を整えます。
また、作業中に外壁や床を傷つけてしまわないよう、周辺をしっかりと養生することも大切です。
さらに、古い雨樋の中には落ち葉やゴミが溜まっていることが多く、取り外すときにそれらが飛び散る恐れがあるため、事前に軽く掃除をしておくとスムーズに進められます。

今回は新たに取り付ける半丸型の雨樋に合わせて、専用の支持金具を取り付けていきます。
使用する金具は鉄製で、外観に配慮して茶色のメッキ塗装が施されたものを選びました。
これは設置する雨樋の色味に合わせたもので、全体の見た目も自然に仕上がるよう配慮しています。
固定の際は、どのような下地材であってもステンレス製のビスを使用するのが安心です。
というのも、釘で固定した場合、長い年月の中で抜けてくるリスクがあるためです。
使用する部材や固定方法については、施工前にしっかり確認しておくと安心ですね。

雨樋の固定金具を取り付ける際には、排水がしっかり機能するように「勾配の調整」がとても重要なポイントになります。
屋根に降った雨水をスムーズに流すためには、わずかに傾きをつけておく必要があります。
傾きが甘すぎたり逆になっていたりすると、水が途中で溜まってしまい、詰まりやあふれの原因になってしまうことも。
そこで、施工の際には「水糸」と呼ばれる糸をピンと張り、まっすぐな基準線をつくって勾配を正確に調整していきます。
この工程を丁寧に行うことで、長く快適に使える雨樋に仕上げることができます。

雨樋をしっかりと支えるためには、固定金具の取り付け間隔も重要なポイントになります。
一般的には、約60cmごとに取り付けるのが目安です。
間隔が広すぎると、雨水の重みがかかるたびに樋がたわみやすくなり、見た目だけでなく排水機能にも影響が出てしまいます。
特に半円状の形をした半丸型の雨樋は構造上たわみやすいので、金具の数や配置には十分な配慮が必要です。

今回は、新しい雨樋の取り付け作業に入ります。
設置するのは「パナソニック製の半丸105」というタイプで、住宅用として広く使われている定番の雨樋です。
現在では角型タイプの雨樋も人気を集めていますが、半丸型を採用しているご家庭も依然として多く、馴染みのある形状です。

雨樋をつなぐ部分には「継ぎ手」という専用の部材を使用して接続します。
この接続には専用の接着剤を使用しますが、塗布が不十分だとそこから水漏れが起きる恐れがあるため、丁寧な作業が求められます。
取り付け後には実際に水を流して、きちんと流れるか、水漏れがないかを確認しておくと安心です。

これまで使われていた雨樋は、針金で本体と金具を固定する方法が取られていました。
しかし今回使用するタイプは、固定金具にあらかじめ留め具が付いており、工具なしでカチッとはめるだけで取り付けられる仕組みです。
作業効率も良くなり、従来のように針金が経年劣化で切れてしまう心配もありません。
特に鉄製の針金で留められている場合、サビなどで切れてしまい、台風などの強風で雨樋が外れてしまうケースも見受けられます。
新しく雨樋を取り付ける際には、見た目や素材だけでなく、使用する固定金具の仕様にも目を向けると安心です。

最後に、雨樋の排水部分に集水器を取り付け、竪樋と接続すれば作業は完了です。
ただし、集水器は落ち葉などが詰まりやすいため、水漏れを防ぐために、特に周囲に木が多いお宅では、落ち葉除けのネットを設置することをおすすめします。
また、点検サービスは「無料」で提供していますので、気軽にお問い合わせください。


街の屋根やさんご紹介
街の屋根やさん宝塚店の実績・ブログ
会社情報
屋根工事メニュー・料金について
屋根工事・屋根リフォームに関する知識
Copyright © 2016-2026 街の屋根やさん All Rights Reserved.